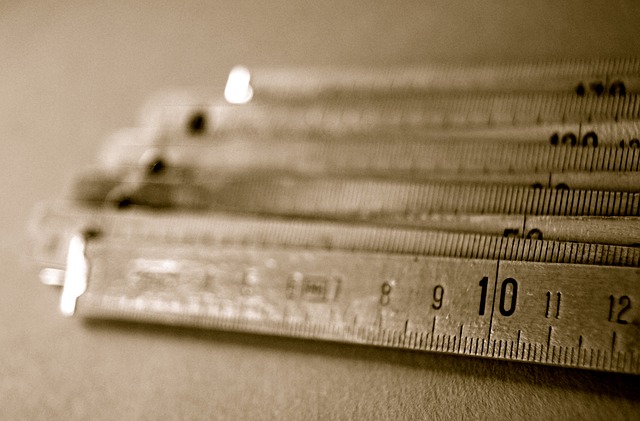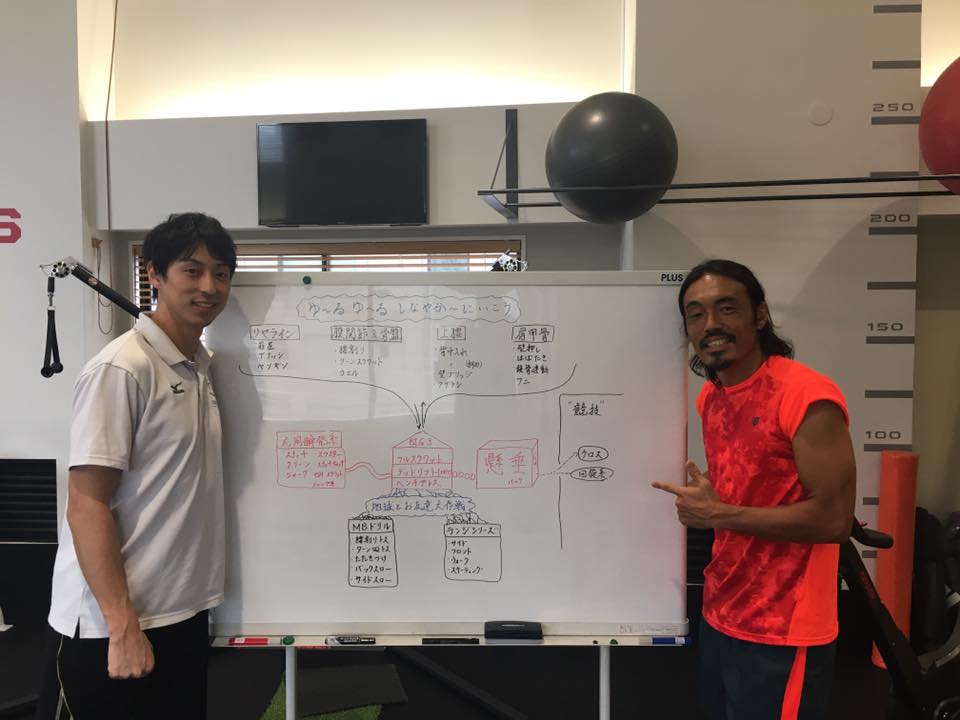安彦考真「好きなことをしてお金を稼ぐ7つのルール」第8回

安彦考真
「好きなことをしてお金を稼ぐ<7つのルール>」
「僕の成功事例を少し教えます」
第8回
連載を続ける中で「安彦さんがどんなふうにして『好きなことでお金を稼いでいるのか』具体的な事例を教えて欲しい」という多くの声が僕のもとに届いた。
僕としては、これまでもたくさんの仕事を創出し、やりたいことをやることでお金を稼いできたから、事例はいくらでも書くことができる。
けれど、それはあくまで僕が成功した事例だ。
そのことをしっかりと理解してもらうため、あえて具体的な事例は出さずに、ここまでもっと根本的なことを伝えようと書いてきた。
多くの人は、すぐに「明確な答え」を求めたがる。
本屋やAmazonの売上ランキングを見れば一目瞭然。今、需要があるのは「誰でもわかる」「すぐにできる」「1時間で身につく」のような謳い文句が踊る実用本たちだ。
本を1冊読むだけで仕事がうまくいったり、お金が儲かったりするなら、この世に悩みや迷いは存在しなくなるはずだ。
けれど、実際はこれらの本を読んでも悩みは解決しないし、年収が倍増することもない。
大事なことは「成功する方法を知ること」でなく「成功者の思考を身につける」こと。
いくら成功者たちが教えてくれる多彩なテクニックを知っていたとしても、今の自分の実情に最適なやり方を実践しなければ望む未来は手に入らない。
僕はこれまでの人生でそのことを嫌というほど体験した。
もちろん僕が失敗したというのではなく「すぐに正解を求める人たち」が次々と失敗していくのを間近でたくさん見てきたという意味だ。
心が変われば行動が変わる
行動が変われば習慣が変わる
習慣が変われば人格が変わる
人格が変われば運命が変わる
運命が変われば人生が変わる
古今東西さまざまな人が引用しているこの言葉こそ、まさに真理を示している。
いきなり行動や習慣を変えようと思っても、望む運命の変化までは辿り着けない。
人生を変えたければ、まずすべきは「心を変える」ことが最優先であり、絶対的な順序なのだ。

それでも、やはり事例があった方が理解しやすいということは僕もわかる。
僕も最初から順調に「心を変える」ことができたわけではないからだ。
僕らは子どもの頃から徹底的に教え込まれている。
小学校では、前に立つ1人の教師に対峙してたくさんの生徒たちが黙って座らされる。そして、教師が求める「正解」(と勝手に決められたもの)を正しく答えることを求め続けられる。
そこに想像力や批判的精神は求められない。むしろそれらは忌み嫌われ、扱いづらい生徒という悪いレッテルを貼られて除外されてしまう。
まだ善悪も判別できない年齢の頃から、僕たちはこうやって大人が勝手に決めた「正解」(らしきもの)だけを返答する心に刷り込まれ、習慣化させられ続けられてきた。
いつの間にか、僕たちはそれが当たり前のことだと無条件に受け入れ、それ以外のやり方は間違ったやり方だと思い込まされてしまっていた。
たった1つの正解なんて(数学的計算問題など一部例外を除けば)あるはずはないのに……。
そんな曲がった思考を植え付けられ、そんな誰かにとって都合の良い思考を備えた集団として育てられ、僕たちはある年齢になると社会に放り出される。
「たった1つの正解」なんて存在しない、厳しく複雑な現実社会に。
偏った思考と、間違ったやり方で、武器も持たずに大海原に投げ出された仲間たちは、懸命に真面目にすればするほど、傷つき、苦しみ、壊れていった。「すべて自分が悪い」という間違った思い込みが足を引っ張る、自己責任という名の蟻地獄に落ちていった。
僕はそんな間違った社会にNOを示したかった。
だから、40歳でJリーガーをめざした。
「そんなことできるはずがない」「前例がない」とやる前から絶対に無理だと決めつける間違った社会の思い込みを打ち破り、苦しむ仲間たちを救うために……。

15年ほど前に遡る。
その時、僕はある高校のサッカー部の臨時コーチを引き受けていた。
その高校サッカー部は最近は結果を出していないが、過去に全国大会にも出場経験があり、卒業生にJリーガーが何人もいる実力高校だった。
部員は100人を超え、レギュラーポジションを争うどころか、ほとんどの生徒がベンチ入り、一軍入りさえ難しい競争の厳しい状態だった。
多くの生徒は真面目に一生懸命サッカーに取り組んだ。
けれど、3年間一度も公式戦に出場する機会がないまま引退する選手がほとんどで、正規のチームユニフォームに袖を通すことのないままサッカー人生を終える生徒ばかりだった。
僕はそのことに疑問を持ち、どうにかして彼らに公式戦に出場する喜びを感じてもらえないだろうかと思案した。
まずは自分なりに現状を調査し、改善点を洗い出してみた。
よくよく考えてみれば、学生時代の公式戦のほとんどは勝ち抜きトーナメント戦という形式をとっている。
つまり、1回戦が終わった時点で全国の4000校以上(2019年度登録数)の高校男子サッカー部のうち、2000校近くが破れ去ることになる。
3年生の場合、たった1日、たった1試合で3年間をかけて取り組んだサッカーの晴れ舞台が幕を閉じてしまうということだ。
2019年度、全国で男子サッカー部に所属する選手は約16万3000名。
4000チームが20名のメンバー登録をするとして、自分に当てられた背番号が入ったユニフォームを着ることができるのは約8万人。
単純計算で、男子サッカー部員の2人に1人は年に数回しか行われない重要な公式戦をスタンドから眺めることになるのだ。
これはあくまで単純計算なので、強豪チームほど部員は多くなる。結果、スタンド行きとなる部員の数もより増える。
サッカーが大好きで、3年間をサッカーにかけてきて、努力の結果サッカーが上達し続けた選手たちが、一度も公式戦のピッチでボールを蹴る楽しさを体験できない。チームの勝利に貢献するチャンスを与えられない。
そんな理不尽なことが、なぜずっと黙認されているのだろうか。
僕は毎日日が暮れるまで汗と泥にまみれてボールを追い続けるサッカー部員たちの姿を見て、強い憤りを覚えた。
そして、少しでも彼らの努力を発揮する場を作れないかと真剣に考えた。

2002年、日本で初めてサッカーのワールドカップが開催された。
その時、すでにJリーグの存在は世の中に定着していたし、前回大会で悲願の本大会初出場を果たしていたサッカー日本代表はチケットが入手困難なほど人気沸騰していた。
そんな中で、日韓ワールドカップは開幕した。日本で世界最高レベルのサッカーが毎日披露され、多くの人が実際にスタジアムで観戦したり、テレビで観たりした。
その結果、サッカーファンはもちろん、今までサッカーにそれほど興味がなかった一般の人たちもサッカーに熱狂した。
連日ワイドショーでも人気選手たちの様子が長時間取り上げられた。ベッカムの髪型を真似する若者が続出し、イケメン選手としてトルコ代表のイルハン選手が芸能人並みに注目を集めた。
そして、熱戦を見た人たちは、誰もがボールを蹴りたくなった。
ベッカムのFKやロナウジーニョの超絶テクニックを真似したのは、子どもたちだけでなかった。
サッカーが気軽に擬似体験できるフットサルコートには、運動不足気味のおじさんやスポーツには縁遠かった若い女性が詰めかけ、和気藹々とボールを蹴り合った。
週末は全国のフットサルコートの予約が取れなくなった。平日の夜、それまで居酒屋に集合していたグループがこぞってフットサルコートに集まった。
サッカーが「見るスポーツ」から「するスポーツ」に変わった瞬間だった。

その後、この頃の異常な熱狂は落ち着いたが、それでもフットサルというスポーツは「するスポーツ」として定着し、サッカーファンだけでなく、新たな固定ファン層を築いていた。
ヨーロッパや南米では、子どもの頃は本格的なサッカーの前にフットサルをやらせる習慣がある。
身体の小さい子どもたちにいきなりフルピッチでのサッカーでなく、狭いコートでしっかりとボールを扱えるようにするというのがその理由だ。
ヨーロッパや南米出身のサッカー界のスーパースターたちの多くが、実際に子どもの頃フットサルをやっていたと語っている。
日本はサッカーとフットサルは少し別の競技という感じだが、サッカーの伝統国ではフットサルはサッカーの一種であり「ボールを巧みに扱ってゴールを決めるという点では同じ」という認識だった。
だから特に南米出身のコーチがいる高校サッカー部では早い段階から選手たちにフットサルをやらせていた。
狭いコートの中でしっかりボールをキープできれば、広いピッチに変われば、より自由にプレーできる。そして、狭いぶん1人の選手がボールを触る機会が増えるので、良い練習機会を持てる。
若いサッカー選手のレベル向上にフットサルはピッタリだった。

僕もブラジルでサッカーをしていたから2002年のブームの前からフットサルは身近なものだったし、その競技としての魅力やサッカーのレベル向上につながるという利点もよく知っていた。
だから高校サッカー部に限らず、指導する若い選手たちにフットサルのテクニックを教えることも多かった。
ただ魅せるためだけのテクニックでなく、サッカーで勝利につながるためのテクニックは子どもたちに好評だったし、実際にサッカーの試合でその技を活かしてゴールを決める選手もいた。
その時の僕は頭の片隅で「サッカー部員全員に3年間の集大成となる場を作れないか」と考えながら、部員たちを指導していた。
その時、ピンときた。
「あるじゃん! 彼らに最高の舞台を用意する最高のアイデアが!!」
(つづく)